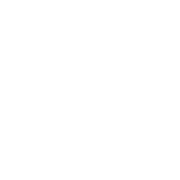京都大学は2025年4月18日、上野恵子医学研究科特定助教らの研究グループが、生活保護世帯の子供の生活背景に応じた効果的な支援システム開発に向けた新手法を確立したと発表した。前例のない分析アプローチで、テーラーメイド型支援システムの開発・普及に取り組む。
上野恵子 医学研究科特定助教らの研究グループは、まず生活保護世帯の子供たちを生活背景に応じて類型化するために、1,275名が回答した質問紙調査から得た情報を用いて、機械学習の手法(ソフトクラスタリング)で生活背景の異なる小集団(セグメント)に類型化した。
次に、この分析で得られた結果をもとに、複雑な支援ニーズをもつ子供たちを支援する専門家へのインタビュー調査を実施。各セグメントの生活背景や特性(人物像)を把握するとともに、それぞれに適した健康・生活支援策について意見を収集した。
その結果、特徴的なセグメントが抽出され、専門家が納得する5つのセグメント「自分で何でもできる子供」「施設にいる子供」「引きこもりの子供」「抽象的な質問に答えるのが面倒だと思う子供」「生活保護利用の世代間連鎖がある世帯の子供」を獲得した。
インタビュー調査の結果からは、身体的健康にとどまらず、社会的健康・精神的健康を支える多様な支援策も示唆された。具体的には、「高等教育進学への経済的支援」「多様で豊かな楽しみを経験するための支援」「継続的に交流できる家族以外の大人の存在」「自身のことを一緒に考えてあげる支援」「家族全体への支援」の5つのセグメントに分けられるという。
今回の分析アプローチは前例がない新たな手法で、研究成果は、2025年4月16日に、国際学術誌「International Journal for Equity in Health」にオンラインで掲載された。現在、同大では研究の成果をもとに、各セグメントに適した支援プランの提示を行うテーラーメイド型支援システムの開発を推進。今後は、子供たちにとどまらず、あらゆる世代の生活保護利用者に健康・生活支援を提供するテーラーメイド型支援システムの開発・普及に向けて取り組んでいくとしている。
川端珠紀