
1965年生まれ、1996年に渡英。イギリス東南部に位置するブライトンで低所得者が無料で子どもを預けられる託児所の保育士として働いた経験を持ち、エッセイ、ルポ、小説でもヒットを飛ばすブレィディみかこさん。2017年『子どもたちの階級闘争』、2019年『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が各賞を受賞したことは記憶に新しいでしょう。今年6月に新刊『SISTER “FOOT” EMPATHY シスター フット エンパシー』を上梓したみかこさんに、イギリスで女性として暮らす目線で見る日本について伺います。4話中の4話めです(1/2/3/4)。イギリスの更年期障害対策、フェムテック導入は「本当にそんなに優れているのか」?――福祉が絞られたという話が出ました。オトナサローネは更年期障害啓発に力を入れていますが、フェムテック分野では必ずイギリスの制度との比較が出ます。実際、女性の健康施策は手厚いのでしょうか。イギリスにはNHS(National Health Service)という原則無料の公的医療サービスがあります。まず家庭医(GP)に登録して、何かあればGPの診察を受け、必要に応じて専門医の診察や紹介を受ける仕組み。子どもが学校や大学に入学するときなんかでも、入学登録のフォームに家庭医の名前を書きます。更年期のケアもとても進んでいます。私も更年期に差しかかったころに、「近所の診療所で、女性の更年期の悩みを話す会が何日何時に開かれるので、参加したい人はここをクリックして予約してください」というメールが定期的にGPから届きました。それほど更年期症状は出なかったのでその面ではお世話になりませんでしたが、でも周囲はいろいろNHSにやってもらっています。最近では2022年に更年期のホルモン補充療法が年間約20ポンド(約4000円)で何度でも受けられる「HRT PPC」が導入されました。出産もNHSを使えば無料です。不妊治療のIVFも20年前の時点ですでに1サイクルは無料でした。当時は40歳が上限で、私はギリギリの39歳で受診したため、病院の人が生年月日を見て取り計らってくれて。この皆保険制度も「無料はやりすぎでは、少しでも費用をとったほうが」という議論があります。NHSの病院の待ち時間の長さが深刻な問題になっているので、近年は特にそうです。が、しかしNHSの成立には歴史的背景があり、イギリス人の多くは、ちょっと外国の人間には理解しがたいぐらいNHSを誇りに思っているんですね。英国人は「病を助ける精神」そのものに極めて大きな誇りを持っている。その納得の理由――国の制度そのものを誇りに思っているというのは知りませんでした。それはなぜでしょう?第二次世界大戦終戦の1945年、救国の英雄チャーチル率いる保守党が優位と見られていた選挙で、労働党政権が誕生しました。労働党は戦争から帰ってきた人たち、貧しくなった人たちのために「ゆりかごから墓場まで」の福祉国家を打ち立て、人々のための国を作ると約束したからです。この労働党政権が無償の医療制度であるNHSを築きました。いまでも英国の子どもたちはNHSの設立理念を学校で教わります。「病とは、人が金銭を払ってする贅沢ではないし、金銭を払って償う罪でもない。それは共同体がコストを負担すべき災難である」。この理念にイギリス人はとても誇りを持っています。昨今米国のリバタリアン的考えというか、自己責任の波が押し寄せて、「NHSなんか抱えてるから財政赤字なんだ」という声もあります。が、この誇りを大切にしている人はまだまだ多い。NHSも労働待遇に課題があり、現場はたいへんなので、ストライキも起きています。ですが、国全体としてNHSの存在はとても大きい。私の連れ合いもがんにり患しましたが、無料で治療してもらえる心強さといったら。安心して病気になれる国です。がんにかかっただけでも辛いのに、治療費の捻出にまで苦しむのは、NHSに慣れた私からするとひどく辛い話です。――そうですよね、日本だと下手すれば「病気になったお前が悪い」「がん患者らしくおとなしくしている」などというような罵倒が飛んできます。病気にも自己責任を求めているのですね。がんにかかるのは災難なのに、酒を飲むな、早く寝ろ、健康になる努力をしていないお前が悪い、そんな自己責任論が健康の分野にも広がるのはどうなのかと思います。私はお酒もめちゃくちゃ飲みますし(笑)、自分の好きなことしかしませんから、ストレスは溜まっていないと思います。私がちらっと知ってる日本の女性たちのことを考えると、みんながんばりやさんで、健康に気を遣うがゆえに「これをやっちゃいけない」とルールを細かく決めて守っている人もいます。私はそういう生き方はできないですね。私はいい加減な人間なので、そういうのはきつい。健康になるために生きづらくなったら元も子もないですし。――抱え込みすぎず、深く囚われすぎない、前向きな考え方を作ることも大切ということですね?ゆるく考えて、何かができないことに深く落胆したりせず、なるようになるよと考えていたら楽になるし、その結果、健康にもなるんじゃないかな。日本の女性って、キャラ弁もそうですが、メイクもみんな道具をいっぱい集めて一糸乱れず正確にやりますよね。それに幸福を感じるのならいいけど、もしも息苦しさや疲れを感じている人がいたら、もっと適当でいいんじゃないかなと思うことがあります。アイスランドではみんなで結託して「女性の休日」を実行しましたが、日本の場合はまず、私も休むからあなたもちょっと休んで、みんなで休もう、しっかり寝ようということから始めてもいいのかもしれないですね。つづき>>>「日本の女性は仕事も家事もなんでもがんばりすぎ」ブレイディみかこが語るイギリスの「いい具合の適当さ」と経済的疲弊の影、『シスター フット エンパシー』『シスターフットエンパシー』ブレイディみかこ・著 1,760円(税込)/集英社アマゾンはこちらからブレイディみかこ1965年福岡県生まれ。作家、コラムニスト。96 年から英国ブライトン在住。2017 年『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』で第 16 回新潮ドキュメント賞、19 年 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で第 73 回毎日出版文化賞特別賞、第2回 Yahoo! ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞、第7回ブクログ大賞(エッセイ・ノンフィクション部門)を受賞。その他著書に『ワイルドサイドをほっつき歩け――ハマータウンのおっさんたち』 『THIS IS JAPAN――英国保育士が見た日本』『他者の靴を履く――アナーキック・エンパシーのすすめ』『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2』や、小説作品に『両手にトカレフ』『リスペクト──R・E・S・P・E・C・T』『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』など。撮影/黒澤俊宏
OTONA SALONE


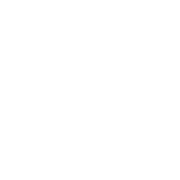
あ。UKも日本に次いで税金の高い国でした😅
資源の無い国の宿命です😢⤵️⤵️