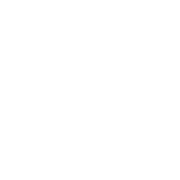子供向けオンライン習い事「ヨンデミー」を運営するYondemyと教育情報メディア「未来図」は、東京大学の学校推薦型選抜合格者への調査をもとに、幼少期の読書体験が合格に与える影響を分析したホワイトペーパーを公開した。同資料では、合格に必要な「頭」「心」「ことば」の3つの力は幼少期の読書体験に影響され、特に感想を語り合うなど「アクティブな読書」が鍵を握っていることを明らかにしている。
近年、大学入試は学力試験中心から、学力に加えて多面的・総合的に評価する方式へと大きく転換している。文部科学省の2024年度の調査によると、学校推薦型選抜と総合型選抜を合わせた入学者の割合は、国立大学で18.5%、公立大学で30.5%、私立大学では59.3%に達し、入試全体の半数以上が一般選抜以外の方式となっている。この背景には、知識偏重から脱し、探究心・主体性・表現力といった「非認知能力」を含めた力を評価する流れが加速していることがあげられる。
東京大学でも2016年から、ペーパー試験の点数だけでは測れない「探究心」「創造力」「学び続ける意欲」などを備えた学生を受け入れることを目指し、学校推薦型選抜を導入した。未来図の分析によると、学校推薦型選抜では大学入学共通テストで8割以上という高い学力だけでなく、卓越した探究活動での成果と、それをプレゼンテーションする高い言語化能力が必要だと分析している。
こうした背景からYondemyと未来図は、学校推薦型選抜で重視される探究心、創造力、言語化能力を育むうえで、幼少期の「読書体験」がどのように寄与するのかをまとめたホワイトペーパーを作成・公開した。
同資料では、東京大学の推薦入試合格に必要な力を「頭」「心」「ことば」の3つの力に分解し、体系的に解説。これらの力の形成には、幼少期の読書体験が大きな影響を与えていることがわかったという。また、合格者へのアンケートやインタビューをもとに分析した結果、単に本を読むのではなく、物事を深く考えたり、内容について感想を語り合ったりする「アクティブな読書」が合格への鍵を握っていることが明らかになった。
文化庁の2023年度「国語に関する世論調査」では、16歳以上の62.6%が1か月に1冊も本を読まないと回答しており、全国的な読書離れが進んでいる。
その一方で、今回の調査では東大推薦合格者の保護者の73.7%が読書習慣をもつことがわかった。また、合格者自身も約8割が小学生のころから読書体験があったと回答しており、家庭と本人の双方で読書が日常に根づいている傾向がうかがえる。東大推薦合格者に「読書は何に役立ったか」アンケート調査したところ、「法学部推薦ではやっぱり求められていると思います。知識量という意味で」(法学部)、「『探偵ガリレオ』シリーズは私が物理学に興味をもつ1つのきっかけの本でもあります」(工学部)、「自分の経験を言語化する能力に役立っていると感じた」(工学部)、「本を読んだ後に、その本の感想を話す経験が、好きなものを語る能力の向上に繋がったと思う」(文学部)といった回答があった。多くの合格者が、読書を通じて「学ぶ力」「考える力」「語る力」を培ったことが合格につながったと語っている。
吹野准