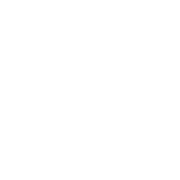1965年生まれ、1996年に渡英。イギリス東南部に位置するブライトンで低所得者が無料で子どもを預けられる託児所の保育士として働いた経験を持ち、エッセイ、ルポ、小説でもヒットを飛ばすブレィディみかこさん。2017年『子どもたちの階級闘争』、2019年『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が各賞を受賞したことは記憶に新しいでしょう。今年6月に新刊『SISTER “FOOT” EMPATHY シスター フット エンパシー』を上梓したみかこさんに、イギリスで女性として暮らす目線で見る日本について伺います。4話中の1話め(1/2/3/4)です。アイスランドでは「女性がストを行った」。でも、これは「日本人女性は努力が足りない」という話ではなくて――海外在住の方のオピニオンというと「日本はダメだ遅れてる未来がないオワコン」と批判されてしんどいことが多い中、本書はさすが俺たちのみかこさんでした。上からではなく、横から立ち話で「こんなことあったんだよ~」と喋っていただいた印象です。はい、私はいつも立ち話のつもりです(笑)。自分自身がラジカルなフェミニストだというつもりは全然なく、「イギリスではこうだよ、友達とはこう話してるよ」と話しているだけのつもりなので、ラジカルと位置付けられると意外です。ただ、日本って、何かしら意見をはっきりと口にしたり、あるいは反論をすると、「え?」と驚かれることがありますよね。そういう点では、私は意見を言うのでラジカルの分類なのかもしれません。この書籍は雑誌『SPUR』2022~25年の連載をまとめたものです。連載のお話をいただいたとき、「もうちょっと日本の女性が元気になって、やれるよ、やろうよ、一緒に生きづらい状況を変えて行こうよ、という気持ちになってもらえる連載にしたいね」と担当さんと話しました。じゃあ、いちばん最初の回に何を書こうかなと考えたとき、近くのカフェの、アイスランド出身の店長さんから聞いていた話が浮かんで。それはアイスランドで1975年に起きた女性たちのストライキの体験談でした。なんと国の9割の女性が参加したというのです。日本どころか、英国でも、女性たちが一日のストライキをやったなんて聞いたこともありませんが、アイスランドでは、世代も階層も違う女性たちが、みんな参加したというのです。その店長さんは当時子どもだったのですが、家で母親やおばあちゃんや叔母さんが話し合っていたのを覚えていて、「私はそんなものに参加しない」と言い張るおばあちゃんに、「だっていつも、仕事場の工場で若い男の子がもらっている賃金のほうが高い、仕事を教えているのは私なのにって文句を言ってるでしょ。いま私たちが何かしないと、孫やひ孫の世代まで、同じことが続くよ」と母親や叔母さんが説得していたそうです。そんな女性たちの地道な対話の輪が国のあちこちで広がって、9割の動員力につながった。ちょっと現代の私たちには信じがたい話ですよね。――その冒頭のエピソードを読み、ああまた私たちは「日本の女性はもっとがんばって戦え」と言われるのか、ごめんなさいもうがんばれませんという気持ちになるのかと思ったのですが、全くそういうことのない作品でした。あとがきまで読むとその伏線が回収される、素晴らしく温かな構成で。ストライキを組織するにあたっていろいろな女性グループが話し合いを重ねるのですが、中道や保守派の女性たちは、ストライキは過激だと反対しました。そこで初老の中道派の女性が「言葉がよくないんじゃないの? 『ストライキ』じゃなくて『女性の休日』にすればみんな乗れるでしょ?」と鶴の一声を発したんです。「ストライキ」という言葉にこだわる左派陣営は不満だったらしいのですが、そこはみんなが一緒に乗れる船にすることを優先して、そのために「女性の休日」という呼び名に決まった。妥協もあり、譲り合いもあり、納得するまで話し合ってまとまっていったプロセスが私にとっては一番泣けるポイントです。これが最も困難なこと、もはや私たちには不可能としか思えなくなっていることですらあるので。ストライキというと労働者たちの運動というイメージがあると思いますが、その日は、勤労者も専業主婦も、一斉に仕事や家事をやめてデモに参加しました。フェミニズム的な運動って、子どもがいるいない、仕事をしているしていないで、とかく分断線が引かれがちですが、主婦も労働者も子どもがいてもいなくても、境界線を取っ払ってみんな参加したから90%にもなったんです。子どものお世話はお父さんがするしかないから、お父さんが会社に連れて行って何とかしました。その日は調理しなくていいソーセージが売り切れたというエピソードが残っている。これらは書中の通りです。女性が大切にされている文化には「サードプレイス」がたくさんある。もっと作っていけたらいいです――この1975年の「女たちのストライキ」、2016年にも同様のストが行われ、結果的にアイスランドでは2018年に世界で初めて男女の賃金格差を違法とする法律が制定されました。よい連鎖が残ったんですね。SNSもない時代に9割集めることができたのは、地べたでみんなが語り合い、説得し合い、組織し合って、繋がっていったからでした。相手の姿が見えないSNSではなくて、生きてる人間の足元から、家族や人間が生活を営む地に足のついたコミュニティが連鎖しあって、連帯というより連合的につながって大きな動きになりました。現在のフェミニズムってイデオロギーの違いで分断や対立を繰り返して、どんどん先細って尖っていく印象がありますよね。でも、女性としてのイシューで繋がって、ここぞという時には一丸となって協働できるシーンは日本でもあっていいんじゃないかって。というのも、アイスランドのストライキに参加した人のドキュメンタリーを見ると、政治的思想の違いは最終的に問題ではなくなるんです。大事なのは女性として抱えている普遍的なイシューでした。男性との賃金格差、子どもを預けるところが少ない、なぜ女性だけが仕事も家事もするんだ、男性も家事をしてほしい。これがこのストの要求の3本の柱でしたが、どれも現代の日本でも共有できる問題ではないでしょうか。こういった地べたからのイシューをフックにすることで、立場や考え方の違いを乗り越えてゆるく帯同して繋がれることはあると思います。SNSで議論するだけではなく、自分の足元から、FOOTから始める行動こそが現実を変えるのではないか、という思いで「シスターフット」と呼んでいます。――なるほど、イデオロギーまで含めた全面賛同でなくてもいい、賛成する意見の部分だけで連帯できれば、もっと大きな動きができると。日本でも個人経営の本屋さんが増えていますが、スペインの本屋さんではバックヤードに地域の女性たちが集まり、ウィキペディアに女性に関する情報を書き込む活動をしていると書中で紹介しています。ウィキペディアの情報にはジェンダーの偏りがあることが知られています。これはウィキペディアに書き込みをしている人が男性であることが多いからだそうですが、人物記事は男性に関するものが圧倒的に多く、女性は著名な人物でも記事が存在しないことがあります。スペインの書店に集まる女性たちは、その状況を解消しようとしている。彼女たちの活動は、それ自体がコミュニティであり、サードプレイスにもなっています。日本にはこうした場が少ないのではないでしょうか。サードプレイスが多い国は民主主義が発達しているのだそうです。女性の人権の問題と、女性たちが集まれるサードプレイスの多さにも関係があるかもしれない。職場でも家庭でもないサードプレイスは、女性にこそ必要な気がします。私は雑誌『MORE』でも連載を持っていましたが、オンライン座談会で読者世代の若い女性たちの悩みを聞いていると、サードプレイスがないって話になりがちでした。職場と家庭以外にふらっと集まれる場所がない。イギリスだとパブがあって、地域の人はみんな集まってきて夏にキャンプに行こうか、チャリティー活動を始めようか、なんて話になったりします。そういう場所が日本にもあれば、いろいろな層の女性たちが集まって互いに新しい知見を得たり、視野も広がったりするのではないでしょうか。――女性もパブに、夜行ってお酒を飲んでいるのでしょうか? 子どもを家に置いて?女性も行きますよ、近所の女性と話したりします。子育てをしている日本の女性って夜、なかなか自分の意思で外に出られないと聞きます、それってすごく不幸なことだと思いません? イギリスはみんな夜は早めに子どもを寝かせちゃうんですよ、19 時とか20時とか。で、寝ている子どもはパートナーに任せてパブとか行っちゃう。つづき>>>移民歴30年のブレイディみかこが語る「他者の靴を履くことでしか見えてこないこと」、それがこれだけ大事な理由『シスターフットエンパシー』ブレイディみかこ・著 1,760円(税込)/集英社アマゾンはこちらからブレイディみかこ1965年福岡県生まれ。作家、コラムニスト。96 年から英国ブライトン在住。2017 年『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』で第 16 回新潮ドキュメント賞、19 年 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で第 73 回毎日出版文化賞特別賞、第2回 Yahoo! ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞、第7回ブクログ大賞(エッセイ・ノンフィクション部門)を受賞。その他著書に『ワイルドサイドをほっつき歩け――ハマータウンのおっさんたち』 『THIS IS JAPAN――英国保育士が見た日本』『他者の靴を履く――アナーキック・エンパシーのすすめ』『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2』や、小説作品に『両手にトカレフ』『リスペクト──R・E・S・P・E・C・T』『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』など。撮影/黒澤俊宏
OTONA SALONE