
鬼ごっこの変種である「だるまさんがころんだ」。小さい頃に友人たちと遊んだことがある人も多いかと思います。この遊びは、鬼が「だるまさんがころんだ」という呪文を唱えることから、この名前がついたと言われています。この遊びは、仲間内で鬼を一人立て、その鬼が他の参加者をすべて捕虜にすることを目的となっており、鬼以外の参加者は、次の鬼になることを回避すべく、鬼に触れた後により遠くへ逃げることを目的とする遊びとなっています。さて、この「だるまさんがころんだ」ですが、地域によっては独特な掛け声もあるとのこと。一例としては、下記のような表現があります。
・くるまのとんてんかん(宮城)
・赤目白目黒目(三重)
・ぼんさんがへをこいた(奈良)
・ぼんさんがへをこいだ、においだらくさかった(京都)
・なないろこんぺいとう(和歌山)
・キャベツの運動会(宮崎)
なお、遊んでいる最中に使用される「だるまさんがころんだ」は、ちょうど10音であるため、10を素早く数える方法としても使われています。アナタはどのように「だるまさんがころんだ」を言っていましたか?是非、ご投稿下さい。
※コチラのコーナーは、何度でも投稿が可能となっています。


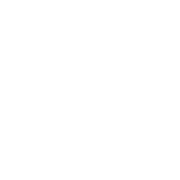
ぼんさんが屁をこいた
も言いましたが、
はーじめのだぁーいっぽ
(初めの第一歩)
でしたね。