
製図や掲示物の作成、また、学校での自由研究の発表などに使用されていた大きな紙である「模造紙」。巨大な紙一杯を使って、クラスの前で発表をしたことなどがある人も多いのではないでしょうか。そんな「模造紙」ですが、地方によって呼び方が違うのはご存知でしょうか。一例としては下記のような表現が使用されているとのことです。
・B紙(東海地方)
・大洋紙(新潟県)
・ガンピ(富山県)
・広用紙(九州)
・広幅用紙(鹿児島県)
・大判用紙(山形県)
「模造紙」という名称が全く利用されず、通じない地域も多いとのこと。アナタは「模造紙」のことを何て呼んでいましたか?是非、ご投稿下さい。
※コチラのコーナーは、何度でも投稿が可能となっています。


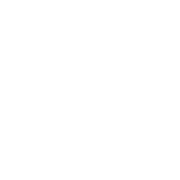
学校でも『模造紙』でしたし、文房具屋さんでも『模造紙』と売られていますし、商品名もカバーのビニールに『模造紙』とありましたし、今でもそうです。
『模造紙』以外の呼び方があるなんて!!
私は日本語教師をしていますが、『メダカ』や『カタツムリ』、『ものもらい』などの様々な違う呼び名の全国分布の仕方は歴史的な時間の経過が関わっています。
しかし『模造紙』は歴史的にはかなり新しいもの。何故そのように呼び方に違いが生じたんでしょうか?気になります。
面白いですね!!