青々と茂った草、青い果実、青物野菜、青信号…日本語には「青」がよく使われれますが、よく見ると「青じゃなくて緑では?」と思ったことはありませんか?他にも、青紫蘇、青蛙、青竹、青葉、青梅、青ねぎ、青海苔など、実際には緑色のものが沢山ありますが一体どういうことなのでしょうか?
これは、日本古来の言葉では「緑」に相当する色も、すべて「青」の中に含まれていたからなんだとか。日本にはもともと「赤」「青」「白」「黒」の4色しかなかったのだそう。赤は暖色系、青は白や黒とも対立して「灰色」や「あいまいな色」などもさしていました。青と緑がはっきりと区別されるようになったのは、昭和26年の学習指導要領で青と緑の区別がされてからといわれています。
また、青には「若い」とか「みずみずしい」という意味もあり、若葉などは黄緑ですが、若いという意味が転じて「青」というようになったんだとか。ケツが青い、青二才、などとも表現しますよね。
信号については、実は国際規格で「赤・黄・緑」に決まっているんだとか。日本に初めて信号が設置されたのはその時は「緑色信号」と法令的に呼んでいましたが、これをなぜか新聞や人びとが「青信号」と呼び出し、青が根付いたために現在では改正され「青信号」と正式に呼ぶようになりました。最近ではLEDが使用される信号機が増え、ずいぶんと青に近くなりましたが、言葉の文化って紐解いてみると面白いですね。
緑なのに「青」信号な理由
コメポ
★★コメント投稿にはID登録/ログインが必要です。
ID登録/ログインへ
ニュース詳細へ
日本語ってやっぱ凄いなぁて思います。
同じことばの『あお』でも、青、蒼、碧、藍などの表現が出来る。
しかもそれぞれの『あお』の色は違ったりしてて。
昔の人は感受性や想像力が豊かだったんだなって、自分の脳みそと比べてしまいました。
同じことばの『あお』でも、青、蒼、碧、藍などの表現が出来る。
しかもそれぞれの『あお』の色は違ったりしてて。
昔の人は感受性や想像力が豊かだったんだなって、自分の脳みそと比べてしまいました。
娘が1歳くらいのころ、色々覚えさせるのに、散歩しながら『これは信号だよ』『赤と青と黄色があるでしょ?』って言いながら、この色は青じゃないんだけどなぁ…と、いつも思っていました。
一応この類いの勉強をした人間から言うと、実は「青」と「緑色」を別けない方が人類全体では多数派なのです。
青と緑色を色として言語上、元々明確に分離しているのはヨーロッパ、それも緯度の高い北方に住む民族の方々だけなのです。
いわゆる金髪に青い瞳の方々がそうです。
ヨーロッパでも南は必ずしも明確ではありません。
何故かと説明するには字数が足りないのでしませんが日本人だけでは無いのですよ。
日本語の四原色は「あか」「あお」「しろ」「くろ」でそれ自体が色や明るさを示す言葉ですが、緑や黄、紫は元々は別なものを示す言葉です。
青と緑色を色として言語上、元々明確に分離しているのはヨーロッパ、それも緯度の高い北方に住む民族の方々だけなのです。
いわゆる金髪に青い瞳の方々がそうです。
ヨーロッパでも南は必ずしも明確ではありません。
何故かと説明するには字数が足りないのでしませんが日本人だけでは無いのですよ。
日本語の四原色は「あか」「あお」「しろ」「くろ」でそれ自体が色や明るさを示す言葉ですが、緑や黄、紫は元々は別なものを示す言葉です。
日本語では一部、黒も「あを」と表する事も有る。漆黒の馬を?青影?と称したり、?髪は烏の濡れ羽色?と言い「緑の黒髪(あをがみとも言う)」などとも言って居る。ひげ剃り跡も鮮やかな場合も「青々とした」などとも言って居る(青髭などと云う場合有り)。白砂青松は青と緑を区別して居ない。
はたして日本語では青も緑も黒も区別をして居ないのだろうか。色の四原則は、中国から伝来したと云われている(青春・朱夏・白秋・玄冬など)けれど、日本では 子亥 児 を「みどり児」などと呼んだりしているので、「緑」と云う語は有ったと思われる。何故に混用する事に成ったのだろうか。
はたして日本語では青も緑も黒も区別をして居ないのだろうか。色の四原則は、中国から伝来したと云われている(青春・朱夏・白秋・玄冬など)けれど、日本では 子亥 児 を「みどり児」などと呼んだりしているので、「緑」と云う語は有ったと思われる。何故に混用する事に成ったのだろうか。
日本には三千年の歴史が有ります。その中で生まれた「言葉」と言う文化。いづれは変化するのだろうけど 大切に守りたいものですね。
特に売上トップの某新聞は 言葉が乱れていて 正しい日本語なんて消えている様です。
特に売上トップの某新聞は 言葉が乱れていて 正しい日本語なんて消えている様です。
アメリカ、ケンタッキー州のニックネームはブルーグラスです。春になり丘一面が若草で埋まり風になびく光景は壮観です。またこの名前の芝生の品種もあります。でも色はもちろん緑です。一方、ブラジルでも信号の進めは緑色(ベルジまたはベルデ)ですが、青(アズール)と言う人をたまに見かけます。理由は分かりませんが、青と緑の混同は日本だけではないようです。
初めて彼にあげた手編みのヘタッピなマフラーは冬でもあり彼に似合いそうな色で“白"でした。今度は彼に青いマフラー編んであげます。“青"の意味みたいな人なので。実は以前から、もう青い毛糸用意してあるのです。
そういえば、祖母や義母が「青いシャツ買ってきたよ」って。見せてもらうと緑色で、「青じゃないじゃん!」って周りにつっこまれてたなぁ。なるほど!歴史があっての事だったのですね。
★★コメント投稿にはID登録/ログインが必要です。
ID登録/ログインへ
ニュース詳細へ


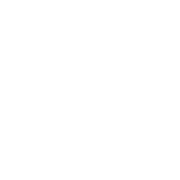
『緑い』『黄い(黄色いではなく)』『黄緑い』は違和感ありまくり。
上の4つは特別なんだな。