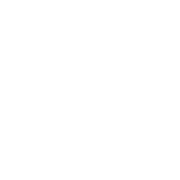日本で一番多いとされる名字は「佐藤」さん、次いで「鈴木」さん、「高橋」さん、とおなじみの名字が並びます。日本の名字は20万種とも30万種とも言われており、大体2000位くらいまでの名字の人で日本の人口の8割くらいを占めていると推測されているようです。では、2001位以下は少数派な名字ばかりなの…?ということで、今回は珍しい名字を集めてみました。
【九】さん
「九」の一字で「く」と読むことから「いちじく」さんと読みます。
【四月一日】さん
4月になると暖かくなり、綿入れの着物がいらなくなるので「わたぬき」さん。昔は一年中、同じ着物に綿を入れたり抜いたりして過ごしていたようです。
【小鳥遊】さん
小鳥は鷹のような強い鳥がいなければ、安心して遊ぶことができるだろう、ということで「たかなし」さんと読みます。こちらは結構有名な「珍名」さんではないでしょうか。
【一番合戦】さん
「いまからするのかい?」が転じて「いまかい」さん。「いちばんまかせ」と読む人も。
【栗花落】さん
栗の花が落ちる頃に入梅することから"つゆいり"が転じて「つゆり」さん。
【鶏冠井】さん
鶏の冠といえばトサカ。トサカの赤い部分が似ていることから「鶏冠」をかえで、と読ませており最初は「かえでい」さんだったものの、いつのまにか「かえで」さんに。
【十】
一見、漢数字の「十」に見えますが、実は、「木」という漢字の両側の払いがなくなっているもの。読み方は「もぎき」さん。木の払いをもいだ形から、というのが由来だそう。正しい漢字は縦棒の先をはねるのだそうです。
読めましたか?漢字って奥が深いですね、アナタの周りの珍名さんも教えてください。
アナタはこの名字読める?
コメポ
★★コメント投稿にはID登録/ログインが必要です。
ID登録/ログインへ
ニュース詳細へ
まさにこの例の中の名前になった友人がいて、結婚するとき読み方で四苦八苦してたら、母が教えてくれました。私は普通の人がいいと思ってたら、メジャーな名前の人と結婚。ただ…フルネーム書くと妙にどっしり感が増してしまいました(^^;)。
[女性/30代/会社員]
2
人がこのコメントに賛成
埼玉県内で、読み辛いからか先祖から漢字を変えて二系統に分かれた一族です。
普通に読めば読めるのに読み辛いからか、何故か学校や病院などで一度も正しく呼ばれない。
人間ドックで朝一番に受付したのに、いつまで経っても呼ばれず業を煮やして聞いたら「再三呼んだ!」と言われ、何と呼んだか確認したら、似て非なる苗字。確かに漢字も三文字だけれども一文字しか合ってないぞ~!!カルテのフリガナを良く見てくれよ~!!
普通に読めば読めるのに読み辛いからか、何故か学校や病院などで一度も正しく呼ばれない。
人間ドックで朝一番に受付したのに、いつまで経っても呼ばれず業を煮やして聞いたら「再三呼んだ!」と言われ、何と呼んだか確認したら、似て非なる苗字。確かに漢字も三文字だけれども一文字しか合ってないぞ~!!カルテのフリガナを良く見てくれよ~!!
祖母井という苗字が出ていましたが、知人は“そぼい“とまんまでした(笑)。
むっちゃお公家さん風で、
高司(たかつかさ)とか
明心寺(みょうしんじ)とか
いたなー。
むっちゃお公家さん風で、
高司(たかつかさ)とか
明心寺(みょうしんじ)とか
いたなー。
四十四願
高寛子
高寛子
名字は普通に読めるのですが「七五三〆」さんという名前の方を知っています。その方は「しめかず」さんとお呼びします。印象に残る方は何時までも忘れませんね…
「動橋町と書いて…いぶりばしまち」
「直下町と書いて…そそりまち」
「花房と書いて…けぶそ」 石川県の加賀地方にある町の名前です。地図を御覧下さいね~
「動橋町と書いて…いぶりばしまち」
「直下町と書いて…そそりまち」
「花房と書いて…けぶそ」 石川県の加賀地方にある町の名前です。地図を御覧下さいね~
今の菅にも読ませてみましょう。麻生と同じ様に。
菅には無理でしょうけど。
菅には無理でしょうけど。
旧姓は功刀・くぬぎ(正確には功のつくりは力ではなく刀ですが)です。
地元ではそんなに少数ではありませんが、県外で正しく読まれたことはありません。
電話で予約や注文をするときは、いつも自分の苗字を連呼してました。
結婚してすごく平凡な苗字になり数年たちましたが、友人からは皆、旧姓で呼ばれます。
地元ではそんなに少数ではありませんが、県外で正しく読まれたことはありません。
電話で予約や注文をするときは、いつも自分の苗字を連呼してました。
結婚してすごく平凡な苗字になり数年たちましたが、友人からは皆、旧姓で呼ばれます。
下水流と書いて、(しもつる)さんを知ってます?
昔、よく行っていた飲み屋のお兄さんに『御手洗』と書いて「みたらい」さんって、素敵な方がいらっしゃいました☆彡
★★コメント投稿にはID登録/ログインが必要です。
ID登録/ログインへ
ニュース詳細へ